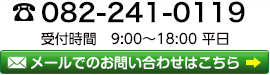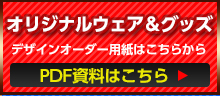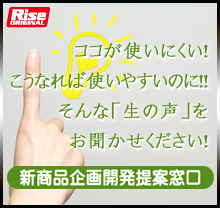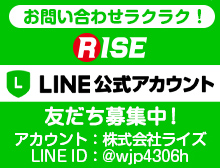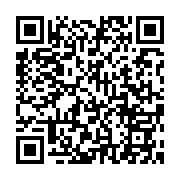全国初!! 木造倒壊建物からの救出訓練


株式会社減災ソリューションズの加古嘉信氏により、本訓練やモジュールの開発経緯などが説明される。

今回の訓練に使用された救助訓練用設備「Rescue Training Module」。2階部分の傾斜角や1階部分の残存空間の高さなどを自在に調整でき、座屈倒壊した木造建物を再現できる。
同モジュールは過去の災害データを基に、倒壊パターンや閉じ込め空間の特性、被災者の圧迫状況などを詳細に分析し、高度な教育効果を持つ訓練環境を実現すべく設計した可搬型の災害救助訓練設備。建物倒壊による閉じ込め現場を安全かつリアルに再現することができ、これまで実現が困難とされてきた実践的かつ体系的な救助・医療連携訓練を可能としている。

模擬建物を例に木造家屋の構造について説明する日本大学理工学部建築学科教授で博士(工学)の宮里直也氏。
2階建て木造建物の倒壊パターンを考慮すると、1階部分が座屈し、その上に2階部分が載った状態になる場合が多い。1階部分に生存者が取り残されているのであれば、残存した2階居室に一次進入し、2階の床、1階の天井を突破して1階へ進入を図る。訓練に使用するモジュールは鉄製の骨格に、実際の建物構造と同じ床や天井のパネルを設定し、切断などを行った後は新たなパネルに交換することで繰り返しの訓練が可能だ。この機能やリアルに再現された木造倒壊建物という環境を活かし、訓練では時間の限り破壊や救出の訓練が実施された。
今回の訓練のもう一つの注目ポイントが「挟圧解除」というテーマだ。兵庫県下消防長会救助技術研究会作業部会が2022年度に研究を行い、2023年には第16回日本地震工学シンポジウムでも発表が行われ注目を集めているのが、倒壊建物内の要救助者の新たな挟圧解除手法だ。
従来は要救助者を圧迫する障害物は上に取り除くというのが定石だった。これはアクセスしやすい上面から順次障害物を取り除いていくシンプルな手法ではあるものの、実際に行うには時間を要し、狭隘空間であれば除去した障害物をどこに逃がすかという問題も生じる。こうした課題を解消すべく編み出されたのが、要救助者の下部を破壊するという手法だ。障害物を安定化した後、圧迫部位周辺の床面二辺(L字)もしくは三辺(コの字)をカットする。これにより要救助者の身体(圧迫部位)が下がり、挟圧が解除されるというわけだ。訓練では参加者がこの手法で実際にどの程度の挟圧が解除されるのか体験し、想定訓練でもこの手法を用いた救出を実施した。

リアルな環境で実施される木造倒壊建物からの救出訓練。
挟圧解除時の床面切断については、要救助者への配慮が不可欠だ。マスクやアイプロテクターの装着はもちろん、要救助者の直近で切断を行うことから保護が必要になる。これについては、その場にある板材などをシールドとして活用する。要救助者とのクリアランスが確保できないといった状況であれば、電動工具ではなく手ノコを用いるなど、現場状況に加えて要救助者の反応にも注視して切断を進めるようレクチャーされた。
木造倒壊建物への進入要領やその内部からの救出要領といった、いわゆる木造CSRMスキルは、実環境に近い訓練環境で行わねば得られぬ内容が多分にある。1階部分が倒壊した木造建物の状況をリアルに再現した上で安全に訓練を行うことができる「Rescue Training Module」は、今まで行うことができなかった実践的な訓練を可能にする唯一無二の存在と言える。同モジュールを開発した株式会社減災ソリューションズでは、自治体・消防・警察・医療機関・教育機関などとの連携を深め、こうした訓練会を全国的に広げていく予定だという。また、消防団や自主防災組織(地域住民)向けの共助訓練への活用も可能で、地域防災力の底上げにも効果が期待されている。
救える命を一つでも多く救うための新たな取り組みに注目が集まっている。
| 本記事は訓練などの取り組みを紹介する趣旨で製作されたものであり、紹介する内容は当該活動技術等に関する全てを網羅するものではありません。 本記事を参考に訓練等を実施され起こるいかなる事象につきましても、弊社及び取材に協力いただきました訓練実施団体などは一切の責任を負いかねます。 |
取材協力:株式会社減災ソリューションズ/日本大学船橋キャンパス
写真・文:木下慎次
初出:2025年7月 Rising 夏号 [vol.38] 掲載