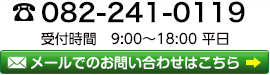3.11 東日本大震災を忘れない[宮城県] interview #01

仙台市若林区を守備する若林消防署。同区は沿岸部に位置し、仙台市内の唯一の海水浴場で知られる深沼海水浴場がある。

若林消防署署隊本部。現場から送られる情報は、どれも耳を疑うような内容ばかりだった。
非番を自宅で過ごしていた引地は、地震発生と同時に「遂に来たか」と、宮城県沖地震の再来を覚悟した。家族の無事を確認すると自転車に飛び乗り、すぐさま署に向かった。署までは自転車で40分ほどの距離。その道すがら、街の様子を確認した。建物やブロック塀の倒壊などはなく、道路の一部が隆起したり、亀裂が入り、信号が止まっている程度だった。だが、安心はできない。これだけの揺れであれば、確実に津波が襲うはずだ。
引地の予想は的中していた。到着した署内の雰囲気が違う。
「荒浜航空分署を含め、津波に襲われている!」
署に到着し、まず耳に飛び込んできた情報はこれだった。
仙台市若林区荒浜の仙台湾に面した防砂林の一角に、仙台市消防航空隊が拠点を置く仙台市消防ヘリポートがあり、ヘリポート内には若林消防署荒浜航空分署が設置され、近隣地区の消防活動の拠点として陸上部隊も配置されていた。同分署一帯を津波が襲っているというのだ。
仙台東部道路より西側、海水により進入不能──

若林区荒浜地区に津波が到達した際の状況。周辺で唯一の高い建物である荒浜小学校の屋上に多くの市民が避難した。
発災当初内陸部の救助対応に当たっていた部隊も、津波襲来後は沿岸部での活動にシフトする。沿岸部からの救助要請を受け現場に向かった部隊から、無線により「仙台東部道路より西側、海水により進入不能」との情報が入る。東部道路は海岸線より3kmほど内陸側を走っている。そこまで広範囲にわたり津波にやられているのか──。
イメージが追いつかず、頭をすぐに切り替えられなかった。
地震の影響によりヘリテレがシステムダウンしており、視覚的情報が入らない。津波が仙台東部道路で止まっていたことから、指揮隊を東部道路上に上がらせ状況確認を行わせた。
見渡す限りが浸水域という状況。可能な限りのボートを集め、東部道路上に前進指揮所を設定して夜通しの活動が行われた。
まずは隊員が入れる場所に入り、要救助者を救出する。しかし、東部道路から少し離れると、足が付かないほどの深さになる。その先はボートによるピストン救出を行った。
応援部隊の到着が折れそうな心を支えた

若林消防署の署隊本部において情報収集・整理にあたっていた引地は、発災直後から現場指揮を行っていた隊員らと交代を行うべく、12日の日の出とともに現場に入った。
ここで初めて目にした光景が忘れられない。
「なんでここに湖があるんだ?」
街並みが激変していた。浸水を免れている個所も、瓦礫で埋め尽くされている。まるで戦地のような光景。実際の現場を目にしても、すぐには状況が理解できなかった。

仙台市消防局や緊急消防援助隊が前進拠点として使用したのが仙台東部道路。
文字通りの不眠不休の活動が続く。気が張っているためか、疲れるといった感覚はなかった。
受け入れがたい目前の光景に、動転もした。しかし、現場で活動する隊員の誰もが、とにかく救助しなければという強い使命感により突き動かされていた。
木造家屋が並ぶ住宅街。ビルなどもなく、建物2階の屋根の上や学校の屋上に人々は避難していた。余震の発生や津波注意報により何度も中断を余儀なくされながらも、手振り要救助者などの救出は2日目で完了した。発災時はとにかく寒かった。救出後に「あの辺りから声が聞こえていたが、夜が明けたら聞こえなくなった」という要救助者からの情報を幾度となく聞いた。すぐに救出できていればと、悔しさが募った。
被災エリアは広大で罹災者数も把握できない状況。こうした先の見えぬ中で引地らを勇気付けたのが、緊急消防援助隊、そして警察や自衛隊といった応援部隊の到着だった。
「ありがたいという感謝の気持ちと、心強さを貰えた思いでした」
要救助者が自分たちの到着を知ったときの安心感。それと同じものを感じることができた。
執念の捜索活動

南長沼に行方不明者が流されている可能性があるため、沼の水を抜き去っての捜索活動を実施した。
以降は行方不明者の捜索にシフトする。日が経つにつれ水が引き、入れるエリアが広がる。昨日は見えなかった場所が見えるようになるので、検索を実施する。水没車や原形をとどめた建物はその内部まで検索をかけ、漏れがないよう何度も同じとこを確認した。
「お子さんを探す親御さんがいました。なんとしても帰してあげたいと捜索を続けましたが、どうしても見つけてあげられなかったことを覚えています」
ひとりでも多く、そして早く家族のもとに帰してあげたい。その一心で、隊員らは地道な活動を続けた。
「捜索活動は、下だけを見ていてはだめなんです」と、引地は言う。
足元の瓦礫や土砂にばかり目がいきがちだが、高い木の上で御遺体が発見されることもあった。それだけ波高がすさまじかったのだ。
だから、足元はもちろん、高い位置もくまなく検索する必要があった。
また、管内にある南長沼に行方不明者が流されている可能性があった。そこで、沼の水を抜き去っての捜索活動が実施された。
できることは、すべてやる。
執念の捜索活動が続いた。
5年を経て
「あの災害を経験していない人にとっては『もう5年』なのかもしれませんが、私たちにとっては『まだ5年』という感覚。現場では瓦礫もなくなり、復興が始まっている。しかし、その地域で生活していた私たちは、街並みがきれいになっても、そこに何があったかを思い出してしまう。心の整理が付いていないんでしょうね。いつ、どんなことで整理が付くのかはわかりません」
5年という月日は、長い。しかし、未曾有の大災害を前に、5年で心がリセットできるはずもない。現実を受け止め、次に繋げるべく、一歩ずつ前進を続けるのみだ。
「大きな被害、そこでどのような活動が行われたのかを伝えていかねばならないと思う。若い職員には、これだけの大災害でも、地域の人々や関係機関との連携のもと対処できたという事実を覚えておいてほしい」
人知を超えた巨大災害を前に、人間の無力さを感じさせられる場面もある。だが、強い気持ちと、日ごろやっていることをしっかりやっていれば対処できる。
未来を担う若い隊員にこう伝えて行きたいと、最後に力強く語ってくれた。
現場写真提供:仙台市消防局
インタビュー:伊木則人(株式会社ライズ・代表取締役)
文:Rising編集部