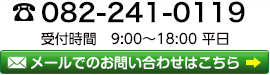3.11 東日本大震災を忘れない[宮城県] interview #03

塩釜地区消防事務組合は、塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町の2市3町で構成され、約150平方キロメートルの管内を1消防本部・5消防署・1出張所・事務局(2課)で守備する広域消防本部だ。
このうち、多賀城市にある多賀城消防署は管内唯一の特別救助隊が配置されており、主要幹線道路や高速道路を利用し管内全ての救助事案に出動している。
小島が率いる特別救助隊では午前中の救助訓練を終え、事務室でデスクワークを行っていた。そして14時46分。今まで経験したことのない強い揺れが、非常に長く続いた。

ショッピングセンター内部の状況。
揺れが収まると同時に庁舎の被害状況を確認し、消防車両を車庫から出す。すると、大津波警報発令という情報が飛び込んできた。小島らは沿岸部付近の警戒広報の下命を受けた。
「いいか、落ち着いて行動しろ!」
ライフジャケットの着装を隊員へ指示し、小島は自らにも言い聞かせるように言った。
1隊3名にて救助工作車へ乗り込み、沿岸部へ向け出場する。多賀城消防署を後にして間もなく、無線にて救助指令が入った。
「──ショッピングセンター内にて天井が崩落し、数名が挟まれている模様」
「救助1了解、出場する」
沿岸部へ向け走っていた救助工作車は、進路を内陸側にとりそのまま出場する。出場途上に車窓から見える風景は、普段と大きく異なることはなかった。大きな揺れであったため、一般建物の倒壊を心配していたが、見る限り大きな被害はないようだ。そう思った矢先だった。とある商業施設の前を通過した際、その建物の外壁が大きく破損し、鉄骨が全て剥き出しの状態になっているのを確認した。被害は、やはり大きい。車内の全員がそう思った。
発災直後の救出活動
指令より約8分ほどで現場であるショッピングセンターに到着する。先着隊からの情報によれば天井が崩落し、大きな空調配管が落下。その下に母子が挟まれているという。マット型空気ジャッキでのリフトが必要であるとの情報を受け、隊員に資機材準備を指示し、小島は現場確認に向かう。

安全な場所に設置された応急救護所。
建物内は真っ暗で、床には商品やガラスの破片が散乱して足の踏み場もない。また、破損した消火配管から水が流れ出し、雨のように降り注いでいる。止まったエスカレーターを上がり2階の現場に着くと、消防隊によりすでに母親は救出されていた。残る子供の状態を確認すると、意識がない。手を握り「頑張れ!」と声を掛けを続ける。この子に圧し掛かるのは直径50cm、長さ30m以上の空調配管2本。とても人力で持ち上げられるものではなかった。
配管と床とのスキマが小さかったが、何とか2か所のリフティングポイントを確認。隊員が資機材を携行してくると直ちに設定し、マット2枚へ同時に送気させながら、ゆっくりとリフトアップした。体幹より約5cmの間隙を作成し、子供を引き出して救出した。
救急隊へ子供を託すと、小島らは店員と手分けして店内に逃げ遅れがいないか検索を実施した。
津波襲来
店内に逃げ遅れがいないことを確認すると、管轄の消防隊に引き継ぎ、救助隊は出場体制を整える。
「救助が多くなるのはこれからだ。しっかり水分を補給しておけ」
地震発生からすでに1時間が経過していた。無線にて引揚げ報告を入れると、当初の任務であった大津波警報に伴う警戒広報を実施するよう下命された。小島らは道路状況と被害調査も兼ね、出場ルートとは別のルートで沿岸部へ向かった。

多賀城市内の津波襲来時の状況。
主要道路は交通量が多いものの、パニック状態ではない。道路も所々で段差が生じているが、大きな陥没はなく、通行不能には至っていない。間もなく多賀城市の市街地へ入るというところで、無線から耳を疑う内容が飛び込んできた。
「津波については、七ヶ浜消防署下の○○酒店付近まで到達」という通信に対し、指令室が「○○酒店ですか!?」と聞き返している。それもそのはずだ。七ヶ浜町は同本部の中で最も沿岸部に面しているが、消防署は高台に向かう中腹に建っている。そのすぐ下まで津波が迫っているということは、町全体が津波に飲まれていることを意味している。にわかには信じられなかった。この津波到達情報をもとに、救助隊は一旦帰署するよう新たな下命を受ける。多賀城消防署までは約1km。多賀城市役所付近を通過し、救助工作車は多賀城駅前の砂押川にかかる橋を通過しようとしている時だった。
「おぉ!津波だっ!!」
車内で、全員が同時に声を上げた。
決断

幹線道路上は被災車両や漂流物で通行できない状況となった。
砂押川の下流から、波しぶきを上げ、分厚い津波が押し寄せてくる。
「橋を渡ったところで車両を止めろ!」
救助工作車を路肩に止め、小島らは走って橋まで戻る。川の水位は瞬く間に上昇し、津波が飲みこんだ船が回転しながら押し寄せ、橋の欄干に当たって粉々に砕け散る。この状況では橋が崩壊するかもしれない。だが、この状況を知らない車両や人々が普通に行きかっている。小島は隊員に通行車両と歩行者を全て避難させろと指示する。
隊員と三方に分れて避難誘導を行う。川からは今にも水が溢れ出しそうな状況だった。その時、状況が一変する。小島らが警戒していた砂押川ではなく、反対の市街地の国道から津波が迫ってきたのだ。それを見た人々により、周囲はパニック状態となる。
既に交差点は、車でごった返し、進むことも戻ることもできない。浸水が始まり徐々に水位が上がってくるが、それでも車から降りようとしない人々がいる。「早く車から降りて避難しろ!」窓を叩きながら小島は叫んだ。救助工作車は渋滞車両に進路を塞がれた状態。
<もう車両は諦めよう・・・>
小島は苦渋の決断をした。これからの活動を考えれば、唯一の救助工作車を失うことは避けたい。しかし、現実問題として、目の前に救いの手が必要である市民が数多くいる。小島らは人命救助を続けることにした。
水位は更に増し、人が乗ったまま流される車両が数多くあった。水位に気をつけながら救出し、車から救助した人や通行人は近くの複合用途ビル2階に上げた。
いよいよ水位が腰から腹の高さとなる。最後に老人2名を救助。再度辺りを見渡すが、人影は確認できない。何とか間に合った。だが、この段階で水位が首の高さまであがっていた。これ以上の活動は困難と判断し、付近の住宅の2階に緊急避難した。
「至急、至急、至急! 救助1から本部・・・」
状況報告を入れようとするが、本部につながらない。完全水没により携帯無線機は送信不能となってしまっていたのだ。
2階から見下ろすと、水位は更に上昇。車が次々に流され、コンビニエンスストアの駐車場に吹きだまっている。大粒の雪が降り始め、無音になった街中にショートしたクラクションが鳴り響いていた。
憔悴
外は大粒の雪が舞っている。
濡れた救助服が纏わりつき、身体の熱を容赦なく奪っていく。とにかく寒い。身体がガタガタと震える。住民の方が提供してくれた毛布を借り、隊員同士密着してなるべく体温の低下を防いだ。通信手段が途絶えた今、何よりも情報が欲しい。住民の方に携帯のワンセグ放送を見せてもらうと、千葉県市原市で発生している石油コンビナート火災の状況や、仙台市の沿岸部が津波に飲み込まれれる映像が流れていた。
いったいどうなってるんだ・・・。
気になり外を見ると、数か所で煙が上がり始めているのが見えた。一刻も早く署へ戻らねば。気は逸るが、水位は全く引く気配を見せず、むしろ上昇を続けている。現在地から署までは約1kmで、そう遠い距離ではない。しかし、どこまで冠水しているのか見当もつかない中で、流れのある津波浸水域を脱出するのはあまりにも危険過ぎる。辛うじて受信のみできる携帯無線機から、所属の他の部隊と前進指揮本部が高台に避難していることが確認できた。

冠水により通行不能となった市内の道路。
すでに避難してから1時間が経過した。あたりはうす暗くなり始めている。ここで、手にしていたもうひとつの通信ツールである特定小電力トランシーバーから聞き覚えのある声が入ってきた。反対番の救助隊長の声だった。現場での部隊間情報伝達用に活用するこのトランシーバーは、市街地や住宅街の場合の通話距離は条件が良好だとして数百メートルが限界。つまり、手を伸ばせば届く範囲に仲間がいるということを意味していた。
すかさずプレストークスイッチを押下し、交信を試みる。つながった。どうやら反対番の救助隊長率いる隊は、現在地から約150mほど離れた位置で警戒を行っているという。
署までの約1kmから、約150m先の仲間の元へと、目標地点までの距離はぐんと短縮された。小島は脱出のタイミングを熟考した。
脱出

小島は自問を続けた。
まずは脱出開始のタイミング。移動距離は約150m。だが、水位はまだ180cm程はある。一方で、完全に暗くなってからの脱出はリスクが高すぎる。水位の状況、そして辺りの明るさの変化を見つつ、ギリギリまで待つことを決めた。
避難してから2時間が経過した18時。この段階で水位は10cmしか引かず、まだ170cm程はある。しかし、停電した街が夕刻の闇に包まれるのは目前だった。
──今しかない!
小島は隊員らに脱出開始を指示。住民へお礼の言葉を伝えると、水の中へと続く階段を下りる。先頭の小島が、水に足を浸ける。突き刺すような水の冷たさに声を失った。

脱出に活用したパレットは、周辺の酒店から流れてきたものだった。
「深みに気を付けて、壁伝いにいくぞ!」
ゆっくりと道路に出たところで、流れ着いた貨物用パレットを発見する。フォークリフトで荷物を運ぶ際に使用する、樹脂製のパレットは水に浮く。これを浮き具代りに、掴まって移動することにした。「足は着いているか?」と隊員に確認すると、「つま先だけです」「ギリギリです」と答えが返ってきた。
水底は当然全く見えず、色々な障害物に足をとられる。交差点に差し掛かると水深は更に深くなっていた。水没した車両を手で掴み、片足で跳ねるように少しずつ前進する。やっと冠水していないエリアが視界に入った。だが、進みが小さいだけに一向に接近できない。
あまりの寒さに声も出なくなる。小島ら3人は互いに声を掛け合い、前進を続けた。
赤色灯が回る化学車のもとへようやくたどり着き、反対番の救助隊長と合流できた。すばやく状況を報告すると、その化学車で、一旦多賀城消防署へと戻った。
再び、現場へ

脱出経路の状況。写真手前から奥に向かい進んでいった。
多賀城消防署は津波被害を免れていた。
署に着いてすぐに当直司令や副署長に対し現場の状況、車両水没の報告を行う。その後、身体を温める方が先と考えた小島は、隊員とともに着替えを済ませ、温かい飲み物で暖をとった。
「あの時避難させてなかったら、大勢の人が流されてましたよね・・・」
隊員がつぶやくように言った。最大の武器である救助工作車を失い、緊急避難を余儀なくされた現実。小島自身がそうであるように、隊員も心に大きなダメージを受けている。このわずかな休息の間に、折れかけた心を立て直すことが必要と考えた。
「俺らのとった行動は、絶対に間違っていない。自信を持て!」
力強い小島の言葉に、隊員らに再び力が漲った。
時間の経過とともに津波による浸水域が徐々に判明し、そこからの救助要請が多数入電する。ボート隊が編成され次々と出場していく。
津波により救助工作車を失った小島らは水難隊として、水難救助資機材を積載した搬送車で活動することになった。ドライスーツを着装すると、再び現場へ向かった。
孤立者の救出
津波襲来により多数の孤立者が発生。20時の段階でも方々で電柱や車の上で孤立している人がいた。さらに、その多くはズブ濡れ状態で、氷点下の屋外で助けを待っていた事から、低体温症の危険にさらされていた。一刻も早い救助が必要であることから、多賀城橋南側付近に多賀城隊活動拠点を設定し、アルミボートやゴムボート等を活用しての活動準備を行っていた。
だが、浸水域は水深もまばらで、多数の漂流物や瓦礫等が散乱していることから船外機を使用する事が出来ない。すると、そこに水上バイクを活用し知人を救助している住民がいた。水上バイクであればこうした状況でも迅速な水面移動が可能だ。協力を要請したところ快諾を得ることができ、水上バイクとアルミボートをロープで連結しての救助活動が始まった。

ボートによる救助活動の様子。
救急隊長からガソリンスタンドの屋上にレベルの悪い男性がいるので、そこから着手して欲しいとの要望があった。小島らは直ちにその男性の元へ向かい、三重もやいによる救助方法により水面上で待つアルミボートへ一次救出し、救急救命士が観察を行いながら、応急救護所へ搬送した。
その後も孤立している人を次々アルミボートへ乗せ、何度も水上バイクによる搬送を行った。この活動は明け方5時頃まで続き、100名以上の救助に成功した。
皆さんは生きてる。・・・頑張りましょう!
ボート隊が要救助者を搬送している間に、小島らは次の声を求めて検索を実施する。
声のする方へと向かうが、真っ暗な上に水底がどうなっているのか全く分からない非常に危険な状況だ。そこで、流れてきたタイヤに掴まり移動することにした。
声のする建物に向かい、要救助者をピックアップ。そしてボート隊に引き継ぐ。救出しながら移動を進めると、道路に沿って堀がある場所にやってきた。しかし、水深が深く道路と堀の境が全くわからない。深みに足をとられては危険だ。幸いにも小島と、バディーを組んでいた隊員もサーファー。そこで、浮き具代りにしていたタイヤに乗ってパドリングで進むことにした。
大通りに面した牛丼店にたどり着く。屋根の上に14人が避難していた。同時に到着したボートにはすでに数名が載っていたので、屋根から4人だけを降ろして乗せる。ボートが戻ってくるまでの間、屋根上の看板を風除けにして待機することにした。
「こうやってここにいるのも何かの縁。自己紹介でもしましょう!」と小島が切り出し、自己紹介を始めた。
「自分は多賀城消防署で救助隊長している小島と言います。訓練する時はいつも厳しく指導してるから、ボート隊の隊員がここに戻ってくるか心配です」
こんなときだからこそ、ジョークを交えてみた。皆も笑い、少しだけその場が和む。一人ひとり、自己紹介していった。最後に小島がこういった。
「たくさんの人が亡くなってる。でも、皆さんは生きてる。・・・頑張りましょう!」
すると、誰からともなく「だよな。よし、頑張ろう!!」と声を上げた。気力も十分。このグループはボートが来るまで待っていられる。そう確信した小島は、隊員とともに一旦歩いて前進指揮所へ戻った。
命に関わる決断
活動は途切れることなく続いた。翌12日の10時過ぎには浸水域の水位が膝下まで下がる。これにより、宅内などで夜を明かした住民も、水に浸かりながら避難のため動き始めた。何百人という地域住民が冠水している国道を歩く姿は、異様な光景であった。その頃、緊急消防援助隊の長野県隊が到着。指揮車を先頭に整然と隊列を組む緊急消防援助隊を見た時は、『心強い』と心底感じた。
午後からは、小島らは長野県隊救助部隊のナビゲーションを担当しながら合同検索を実施した。市街地をブロック毎に1件ずつ検索していく。庭先、車の下、玄関先。次から次に、ご遺体が発見された。あまりに数が多すぎて、警察の遺体収容も対応しきれず、一時的に消防車両を使用し、遺体安置所へ搬送した。活動中も余震は頻発していた。そして管内で発生していた石油コンビナート火災は、更なる爆発危険があることから半径2キロ圏内に避難指示が出た。

多賀城隊と緊急消防援助隊との調整会議。
夕方になり、この日の活動を終了しようとした時に指令が入った。一般住宅から具合が悪くて避難できないとの通報があった。しかし、先着した救急隊によれば呼びかけても反応がないという。建物は施錠されており、地震や津波による破損がないことから進入口もない。平時であれば警察官の立会のもとにガラスを破壊し内部を確認するが、この震災で警察官も現場に臨場できる状況ではない。無線にて判断を求めるが「現場で判断されたい」との回答。引き揚げるか否か。小島は内部の確認を決断した。隊員にガラスを破壊し窓を開放して内部進入を図るよう指示。宅内を検索したところ、要救助者が2階で胸痛を訴え横になっていた。
よかったと胸をなでおろす一方で、あのまま引揚げていたらとも考えた。現場での決断は、要救助者の生命に直接関わる。決断するにはその理由と根拠が必要だ。難しさを感じた。
家族との再会
この活動を終えた頃にはすっかり日も落ち、震災発生から二日目の夜を迎えようとしていた。
余震が頻発し、津波への警戒も必要であるため、消防署ではなく高台にある大学の構内に全ての部隊を移動させた。夜は、この構内での休息を覚悟していたが、発災前日から勤務していた小島らは、一旦帰宅して家族の安否を確認するように命じられた。やっと家に帰れる。しかし、家族は家にいるのだろうか。皆がそんな不安を抱えていた。
小島は帰宅する前に隊員を集めた。隊員それぞれが今までにない経験をしている。早い段階でデフィージングを行う必要があったからだ。思ったこと、感じたこと、怖かったこと。一人ひとりが話す。
「救助工作車は失ったが、あの場面で避難誘導をしていなければ、もっと多くの犠牲者が出ていた。誰に非難されようとも、自分の判断に自信を持っている。活動は長期化すると思うが、皆で頑張ろう!!」
最後に小島がそう話し、解散した。

現場状況を確認する隊員たち。
救助服のままブルゾンだけを羽織って、車に乗り込む。自宅に通じる道は、冠水などでいずれも通行できない。小島は自宅から1kmほど離れた場所に車を止め、歩きだした。停電により辺りは真っ暗で、恐ろしいほどに静まり返っている。冠水道路を通らなければ自宅へ帰れない。膝上まで水に浸かる。水の冷たさに、あの脱出時の記憶がよみがえった。
ようやく自宅に辿り着く。幸いにも冠水は免れており、カーテン越しにローソクの灯りが見えた。玄関を開けると、息子と娘が泣きながら飛びついてきた。しっかりと抱き締める自分も、我慢していた涙が溢れ出した。
息子は授業中に地震にあい、そのまま学校に待機。娘の通う保育所は、全員で息子の通う小学校に避難。津波の水が引いた後すぐに妻が学校に迎えに行ったとのことだった。
学び、伝えていきたいこと
翌朝も早くから現場に戻り、活動を再開。この後、活動は人命検索活動から、徐々に危険排除活動に移行し、通常業務に戻るまで約4ケ月間続いた。
小島はこの災害活動を通して2つのことを学んだという。

緊急消防援助隊とともに活動を展開。
1つ目は『判断力の重要性』である。
通常の災害では、一分隊として上席者の指揮の下に活動するが、災害規模が大きくなり消防力が分散して活動する場面になると、各々が直面する状況を自ら判断しなければならない場面に直面する。
こうした状況においても、躊躇する事無く『判断』しなければならない。
これは階級に関わらず消防職員として身につけなければならないスキルである。
後輩を育てるという観点からも、普段の訓練や業務の中で「常に考えて判断する」ことを実践させるべきであると感じた。
2つ目は『心が寄り添う』ということである。
通常の災害活動では、平時から有事に駆けつけて活動する。しかし、今回経験した大災害では、自らも被災した有事の状況での活動を強いられた。日頃から要救助者には優しく接するように心がけているが、この震災では『自然と心が寄り添った』ことを覚えているという。強者が弱者を助けるではなく「生きる」という目的のために同じ気持ちであったのだろう。この気持ちは、職を辞する日まで持ち続けたいと思っている。
また、今回の災害では、多くの行方不明者が発生し、時間の経過とともに生存の可能性は薄れていった。しかし、その人々を想う「家族の気持ち」はいつまでも変わらない。たとえ亡骸になろうとも、一刻も早く家族の下へ帰してあげることが、家族の気持ちを救う唯一の方法であったのだ。「人命救助という職務は『一つの命を救うだけではなく、その人を想う人々の気持ちも救うこと』だと改めて痛感した」と、小島は振り返る。
千年に一度といわれる大災害を『想定外』という一言で終らせるのではなく、『自然災害に上限は無い』という観点の下に、今後の災害対応計画を再構築し、併せて住民の防災意識の向上を図る。これこそが、今回の災害で亡くなった多くの方々へのせめてもの報いであると考え、小島をはじめとする塩釜地区消防事務組合の全職員は未来に向け歩みを進めている。
奇跡の生還 ─安倍淳さんの場合─
この災害では様々な形で九死に一生を得た人々がいる。
|
現場写真提供:塩釜地区消防事務組合消防本部
インタビュー:伊木則人(株式会社ライズ・代表取締役)
文:Rising編集部